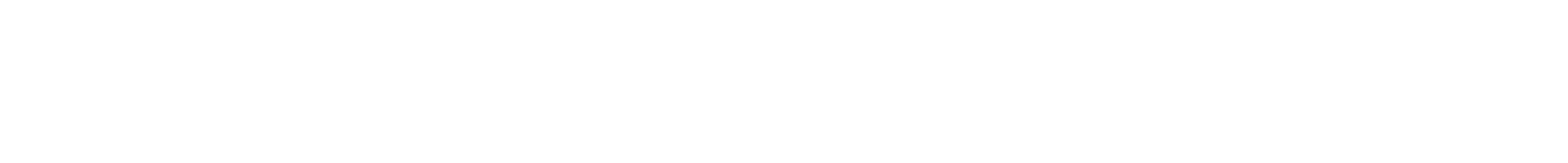【世界の昆虫食文化-001-】フィリピン・ルソン島北部でアドボに使われる“あの昆虫”とは?

※最初に。この記事は決して昆虫食を勧めるものではなく、あくまで「昆虫食文化がある」という事実を伝えることが目的です。
フィリピンには「アドボ」と呼ばれる代表的な家庭料理があります。酢や醤油、ニンニクで作られた調味液に肉を漬け込み煮込んで食べる料理です。
アドボという名前の始まりはスペイン植民地時代のこと。
フィリピン人がお酢を料理に使うのを見たスペイン人によって、酢に付けるという意味の「アドバール(adobar)」と呼ばれたのが名前の由来となっています。
フィリピンの食文化 -フィリピン政府観光省- | https://philippinetravel.jp/travel-meister/content/theme08-01.html
酢を使うこと自体にアドボという意味があり、何を漬けるかは厳格に決められていません。
豚肉や鶏肉、牛肉が使われることが多いですが、ルソン島北部では「コガネムシ」を使用する文化があります。
具体的には以下のようなレシピで作られています。
人びとは、コガネムシ成虫の脚、頭、前胸を取ってから酢と醤油で煮る。
『昆虫食古今東西』三橋淳 著、オーム社、2012年
脚、頭、前胸以外のところを煮ると解釈すると、残ったお腹と翅を食べるということになります。お腹はともかく翅は硬くて食べられるのかどうか分かりません。長時間煮込めば翅も柔らかくなり食べられるのか、硬くても噛み砕いて食べるのか。謎です。
味については、コガネムシの成虫は葉っぱを食べるので、おそらく食べてきた葉っぱに近い味がするのではないのかなーと思います。例えば、サクラやケヤキなど。
ちなみにコガネムシ以外にも以下のような甲虫を食べるそうです。
カブトムシの大きな幼虫やカミキリムシの幼虫も食べる。
『昆虫食古今東西』三橋淳 著、オーム社、2012年
ルソン島北部は山間部なので、こうした昆虫が貴重なタンパク源になっていた(なっている)のだと思います。その証拠として、ルソン島北部で最も食べられている「ケラ」に関して以下のような話があります。
ケラはしばしば稲作地で組織的に採集されているが、日常的な食材とするための飼育法も検討されているという。
『昆虫食古今東西』三橋淳 著、オーム社、2012年
ケラには地中で植物の根っこや茎を食べることで作物に被害を及ぼす害虫としての側面もあります。作物とケラの適度なバランスを保つという意味でも、ケラを食べることは合理的かもしれません。